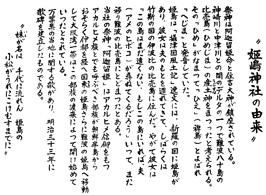東国東郡姫島村にある姫こそ神社(比売語曽神社)とこの姫嶋神社は御祭神が同一であるそうです。
古来より、我々日本民族は氏神を祭って来ました。その氏神を中心として氏がまとまり、「ムラ」を作り、国の基礎となってきました。そして、氏と氏との戦いで強力な方が国を支配してきました。
我々の古里にある姫島は国東半島の沖合い約4kmに浮かぶ周囲4km余りの小島ですがその歴史は古く、古事記にも、いざなき、いざなみの国生みにより出来た島に挙げられております。
何故古事記にもこの小島が採り上げられたのか?それはこの島が「黒曜石(こくようせき)」を産出したことがその一番の理由であろうと筆者は考えております。
姫島村の海岸はその黒曜石が岸辺を埋め尽くし、あたかも神社の玉砂利を想起させてくれます。またこの島は、関門海峡を通じて朝鮮半島にも近くそれゆえに「耀(あかる)姫」伝説に繋がっているのではないでしょうか?
また、大阪市平野区の杭全神社にはその「あかる姫神社」があります。朝鮮半島から渡来してきた人たちは、まず豊富な黒曜石で鏃(やじり)を作り、その優秀な技術で大和政権に請われ姫島へ移住し、またその一部が大阪の平野や生野へ移り、後の坂上田村麻呂を生んだのでしょう!
公害訴訟(尼崎喘息)で全国に悪名を馳せたこの地区ですが、大分と大阪との両姫島の里親制度の様な形で、あのきれいな空気の「姫島村」と相互交流を図り、親睦を深めて欲しい、と願うのは筆者だけの妄想でしょうか? (S.M) |
|